1歳半からドイツ育ちの娘が、ただいま絶賛日本留学中であります。夏休み明けから始まり、来年1月にドイツへ戻ってくる予定。
実は、3年前に兄も同じ学校(関西のとある中高一貫校)で短期留学を経験しており、そのときの充実ぶりが忘れられず、今回もお願いして受け入れていただきました。
日本語は週一でベルリン日本語補習校に通ってきたとはいえ、生活のほとんどはドイツ語。
兄がどこに行っても友達を作ってくるタイプだったのに対し、娘は我が強く、幼い頃から「私は私!」という性格。ふてぶて…いや、たくましく育ってきました。
そんなドイツ育ちの娘が、日本留学だなんて。調和を重んじる日本の学校でうまくやっていけるのだろうか。男子より複雑な“女子の世界”でどう立ち回るのか、正直少し心配でした。
ところが、そんな親の心配をよそに、娘はめちゃくちゃ楽しく過ごしている様子。
先日2時間以上の長電話で話してくれた近況を、今回はまとめてみたいと思います。
15歳の「女子」から見た日本は、息子のときとはまた違い、なかなか興味深いものでした。
最初の2週間は「早く帰りたい」
初めての日本の学校に、緊張と不安でいっぱいだった娘。「日本語が速すぎて、授業やクラスメイトとの会話にもついていけない」と、最初の2週間は苦戦していました。この時は、早くドイツに帰りたいと思っていたそうです。
クラスメイトの子達が気遣って話しかけてくれるけど、気の利いた返事もできないし、話題にもついていけない。兄のようにうまく友人を作れないと激しく落ち込んでいました。
あ、その辺なら、私も経験済みだわ。そこで、ちょいとアドバイスしてみました。

娘は早速行動に移しました。少しずつ「わかる!」瞬間を増やし、徐々に学校に馴染んでいきました。
1ヶ月もすると、「皆面白い子ばかり」「帰りたくない!」とまで言うように。彼女の中で、日本という国が“挑戦の場”から“心地よい場所”に変わっていった瞬間でした。
今では語尾に方言が混じり、会話の合間に「ガチ」を連発しております。ドイツ育ちの気の強さは日本留学中にスイッチが切り替わり、平和に過ごしている模様。
母ちゃんもホッとしております。
義妹一家のホスピタリティに感動
娘がお世話になっているのは、私の義妹の家族。「仕事もしているのに、家事も完璧で、しかもいつも優しい。」と娘。
そうなんです、義妹は賢く優しく美しく、人として私も心から尊敬している素晴らしい人なんです。彼女のきめ細やかな気配りと温かさに心から感謝しています。ご主人、姪っ子ちゃん・甥っ子ちゃんもとーっても優しくて面白い、ハートフルな家族。
そして、日本のお母さんってこんなに一人で全部やるの!?と驚いています。料理のクオリティはもちろん(毎食何品も出てくる)、洗濯機は毎日回すし、お弁当も作ってくれる。で、穏やかで優しいって。
つまりですね、皆様。娘がそう感じるってことは…私と比べているってことなんですよ。とうとう娘が気づいてしまった!大ピンチであります。
確かに私は基本ワンプレート料理だし、料理もお弁当も子供たちに任せることも多いし、洗濯は各自で管理させて私はノータッチ。←コロナでロックダウンした頃に調教しました。
でもまあ、娘はそこで「うちのママは怠けている!」とならず、「日本のお母さんは働きすぎでは!」という方向に行ってくれたのが救いですかね。
とにかく、緊張が続く毎日だった当初は特に、義妹の家でずいぶん救われた様子でした。本当に、足を向けて寝られません。
関西の学校、明るくて最高!
娘が通っているのは関西の進学校。まず驚いたのは、みんな明るくてフレンドリー!
そして──喋るスピードの速さ!
「男子のジョークが本気で面白い!」
「関西人の会話はいちいち面白い!」
「女子が可愛いもの好きで癒される!」
「他のクラスの子まで話しかけてくれる!」
とのこと。
これは全国共通ではなく、関西ならではの距離の近さやノリの良さ、そして、この学校の校風もあるのかもしれません。
それに加えて、娘の“感動ポイント”は細かいところにも。
- 学校がとても綺麗
- トイレがピカピカ
- 体育館の床が光っている
- 学食が安くて美味しい
- 先生が皆親切
どれも当たり前のようでいて、海外育ちの目には新鮮に映るようです。
ドイツの学校では「上履き文化」がなく、校舎内も基本的に土足。そのため、床には砂が入り込み、体育館も決してピカピカとは言えません。しかも学食は──美味しいと思ったことがない!
教師は「学校で勉強を教える人」であり、生徒とは一線を引いています。(そうじゃない学校もあるのかしら?)基本的には生徒のプライベートには関与しません。
日本の学校の丁寧な清掃文化や、温かい文化に触れ、「日本ってやっぱりすごい国だね」と素直に感じたそうです。
ドイツ育ちが日本留学で体験する「授業」
娘が一番驚いたのは、日本の授業スタイル。「ディスカッションやディベートがないんだね」と。これは、3年前に同じ学校に短期留学した息子も同じことを感じていたポイントです。
ドイツでは、社会や倫理の授業で日常的に意見交換が行われます。
たとえば、ディベートの授業ではクラスを2グループに分けて、AとBの対立した立場をそれぞれが担当し、意見をぶつけ合います。
「ヴィーガン派か雑食派」がテーマの場合、本当は雑食派の子がヴィーガン側に振り分けられたりするのも普通。つまり、自分の考えとは逆の立場で理論を組み立て、相手を説得する練習をするのです。
娘曰く「自分のポリシーとは違う意見でものを考えるのが面白い」のだそうです。確かに、思考の柔軟さや論理性を鍛えるにはとても良い方法ですよね。日本語を理解しきれていないのもあり、ドイツの白熱したディスカッション式授業がちょっと懐かしくなるそうです。
数学の授業では「ドイツと解き方が全然違う」「知らない記号を使っている」と。先生の質問に間髪入れずに答えるクラスメイトの姿に「頭いいなぁ」と感心しているそうです。(特進クラスだからかもしれませんね。)
化学の授業は少しわかるけれど、化学物質を日本語名で説明されるとさすがにお手上げ。
唯一自信があるはずの英語の授業も、進行もテストも日本語で説明されるため、意外と難しいそう。それでも「先生の発音がすごくきれいで、ドイツの先生より聞き取りやすい!」と感動していました。
日本とドイツの医療の違い
この2ヶ月間、娘はインフルエンザや寝違えなどで何度か病院へ行きました。(義妹に連れて行ってもらいました。本当にありがとうございます!)
そのときの感想が印象的で、

「すぐレントゲンを撮って診断された!」
ドイツでは、風邪やインフルエンザくらいでは病院へ行きません。もし病院へ行っても、「風邪で熱が出るのは当たり前。ハーブティーを飲んで休みなさい」と追い返される勢いです。薬も滅多に出されません。
たとえ捻挫などで病院へ行っても、未成年のレントゲンはなるべく控えられます。丁寧な触診をし、もちろん薬も出されません。
その文化に慣れてしまっていたので、娘の話を聞いて「そういえば日本はそうだったなぁ」と懐かしくなりました。
話を聞いていて感じたのは、つまり日本は"早く体を楽にすること"、“早く治す”ことを重視しているのですね。義妹も、高熱が続くと娘が辛いのではと心配してくれました。(ドイツだと熱が出るのは当たり前、寝ておけと言われます。笑)
ちなみに、歯医者は断然日本の方が丁寧!ドイツの歯科医院で初めて治療を受けた時、道路工事のようだと思ったのを覚えています。
外科医の友人曰く、外科手術のクオリティも日本の方が高いそうです。やはり緻密で正確な作業は、日本(アジア)の得意分野なのかもしれません。
日本にしろドイツにしろ、結局のところ一番大事なのは、病院に行かずに済む体をつくることですね。
日常に潜む「差別のボーダーライン」の違い
これは息子も言っていましたが、日本とドイツの「差別」のラインが全然違うと。
特に、男女に関する発言で、ドイツだと聞くことのない「男だから〜」「女だから〜」に驚くことが多々あるそうです。
もちろん、そこに悪意はありません。むしろ「男女の違いは当然」と、善意や常識から出た言葉。でもドイツ育ちの子どもたちにとっては、日本留学中に「え?今の言い方、大丈夫なの?」と感じることがあるようです。
これはですねぇ、どっぷり日本育ちの私にはちょっと面倒なテーマだったりします。
たとえば、先生が重い資料なんかを「これは重いから男子が持って。」と言ったとするじゃないですか。これもドイツだと聞かない言葉なのです。
なぜなら、この言葉の裏には「男の子は力が強い」「女の子は非力」という無意識の偏見が隠れているから。
なので、先生は「誰か手伝って」としか言いません。男女を指定すること自体が、すでに古い感覚とみなされるのです。
確かに、確かにその通りなんですけど。そこまで気を遣わなくても良いのでは、と昭和の日本育ちは思ったりします。同じヨーロッパでも、カトリック色の強いイタリアとかではどうなのでしょうね?
娘曰く、息子(=男性)よりも、「女」である自分の立場から見ると、日本社会のこうした“男女の扱いの差”がより複雑に感じられるそうです。
留学の価値とは
ドイツ育ちの娘や息子の日本留学、そして日本で育ち、ドイツに留学していた下宿の子たちを見ていて、つくづく思うことがあります。
留学というのは、語学力や学力をつけることも大切かもしれませんが、
「他文化を受け入れる柔軟さ」
「他国をリスペクトする心」
「自国を客観的に見つめ、分析する思考」
これらを養うことこそ、本当の価値なのではないかと。
娘も息子も日本語がぐんと上達しましたが、それ以上に驚かされるのは、視野の広がりと考え方の深まりです。
SNSの情報や旅行では決して得られないもの。それが、「その国で暮らし、教育を受ける」という経験の中にあります。
1月中旬まで、あと2ヶ月。この先もきっと、たくさんの出会いや発見が待っているはず。日本での経験を思いきり楽しみながら、人として大きく成長してくれたら嬉しいです。
娘が見た日本は、美しく、優しく、そしてドイツと同じように問題点もあるようです。
彼女の中で芽生えた新しい視点が、これからどんな形で育っていくのか、とても楽しみです。
お世話になっている学校関係の皆さまと、夫の家族には心から感謝しています。
海外教育関連リンク
👇おすすめ書籍
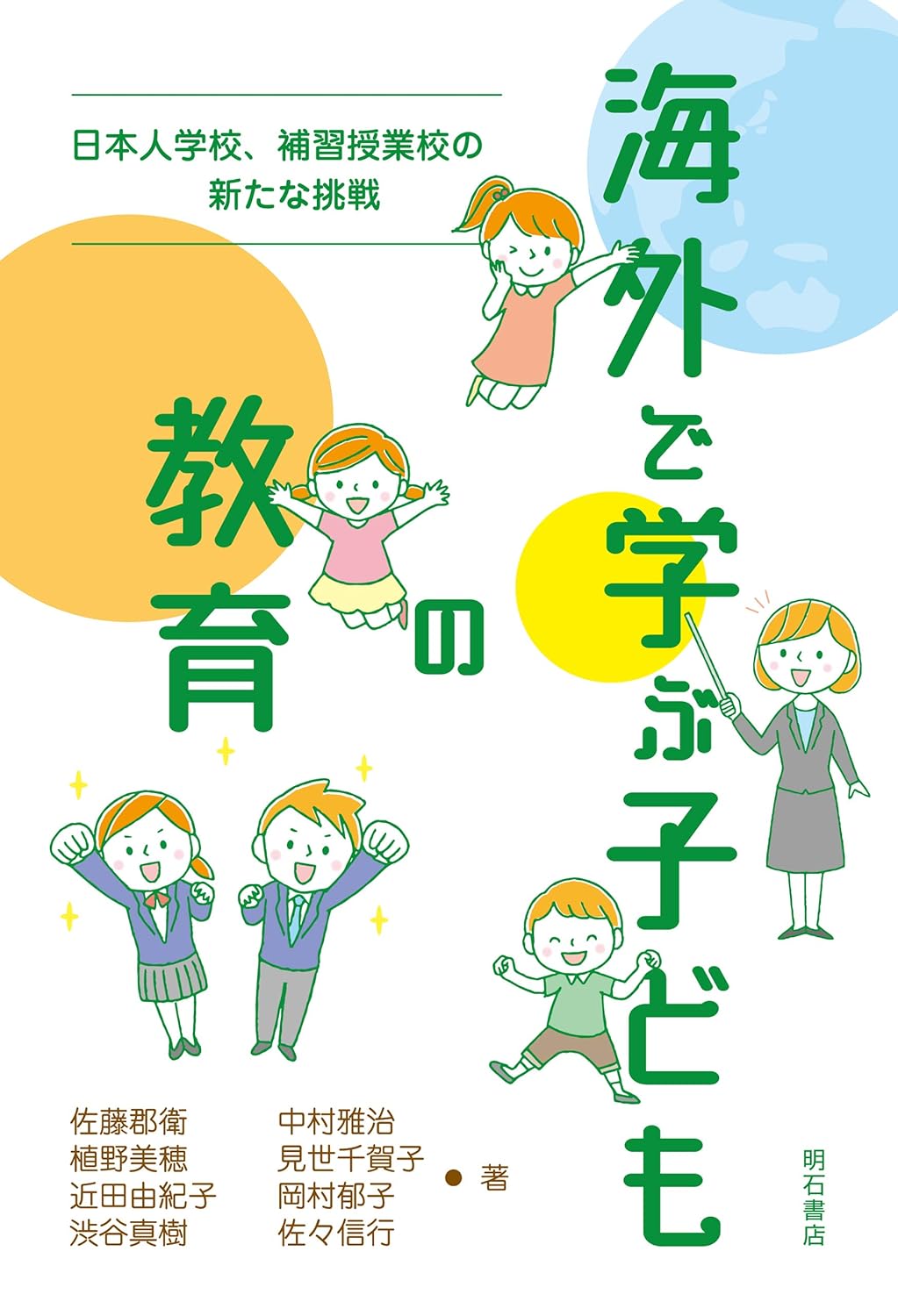
👇在外教育情報
文部科学省の在外教育、帰国・外国人児童生徒教育等に関する総合ホームページ

